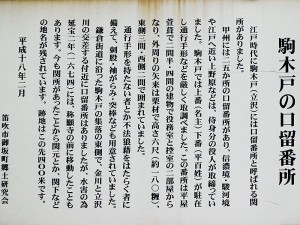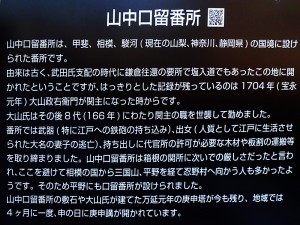長野県認定「信州の伝統野菜」の一つ、太くて根元が曲がったのが特徴の「松本一本ねぎ」は、江戸時代から江戸への信州土産として親しまれてきたそうです。
それも請西藩林家と献兎乃記念碑記事で紹介した「兎の吸物」にまつわる、正月の吉祥を意味する野菜として知られていたとか。(長野県HP参照)
新まつもと物語プロジェクト内『松本一本ねぎ』ページ(http://youkoso.city.matsumoto.nagano.jp/food/?page_id=5043)で徳川家の先祖の有親(ありちか)親子を林藤助(はやしとうのすけ)がもてなした吉例として将軍家で正月に出す『兎の吸物といっしょに使われたのが、松本一本ねぎ』と、詳しく書かれています。
▲早速、松本市のそば処 吉邦 (きっぽう)さんで松本一本ねぎ入りの鴨南蛮蕎麦を食べてきました。
葱といえば鴨。なかなかお目にかかれない肉厚の鴨がさっぱりとした一本ねぎと合って、脂もほどよく熱を溜めて体が芯まで温まります。
葱に興味があることを示すと、店主さんが松本一本ねぎのあれこれをお話してくださいました。
なんと厨房用の一本ねぎも見せて貰えました! 特徴通りに曲がっていて、泥を落とした白い肌がとてもつややかで綺麗ですね。霜にうたれた寒い時期、今が食べごろとのこと。
美味しいお蕎麦とためになるお話をありがとうございました!
* * *
松本から江戸……新宿へ帰る際のお土産には信州芽吹堂の『松本一本葱佃煮』を買いました。
青さ海苔との佃煮で、とってもご飯に合うんですよ~
信濃人の誇れる伝統の葱が、現代人にも広く伝わるといいですね。